黒い迷宮【リチャード・ロイド・パリー】
黒い迷宮
| 書籍名 | 黒い迷宮 |
|---|---|
| 著者名 | リチャード・ロイド・パリー |
| 出版社 | 早川書房(528p) |
| 発刊日 | 2015.04.25 |
| 希望小売価格 | 2,484円 |
| 書評日 | 2015.07.12 |
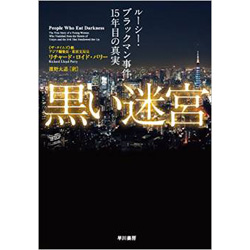
ルーシー・ブラックマン事件を記憶されているだろうか。2000年7月、東京・六本木のクラブでホステスとして働いていた元英国航空客室乗務員、ルーシー・ブラックマン(21)が失踪した。当時のブレア英国首相から森総理に直々の捜査依頼があり、大がかりな捜査態勢が敷かれたことで話題になった。
3カ月後、別件で実業家の織原城二が逮捕され、その4カ月後に彼が所有するマンション近くの三浦海岸洞窟でルーシーのバラバラ死体が発見される。起訴された織原は、同じような手口で別の女性を死に至らしめた準強姦致死罪やルーシーの死体遺棄罪などで無期懲役が確定した。
著者のリチャード・ロイド・パリーは英国「ザ・タイムズ」紙のアジア編集長で東京支局長。日本に20年滞在している手練れのジャーナリストだ。「ルーシー・ブラックマン事件 15年目の真実」というサブタイトルをもつ『黒い迷宮』は、この事件を追ったノンフィクション。犯罪の舞台となった六本木の、外国人と日本人が入り乱れる水商売の闇に入り込んで事件の真相に迫っている。
それだけでなく、たびたび来日して解決を訴えたルーシーの家族や友人、別の被害者であるオーストラリア人女性の家族や恋人を取材して、この事件がいかに彼らに傷を与え、家族をばらばらにしてしまったのかを明らかにする。日本では詳しく報道されなかった織原の生い立ちについても、家族や友人に接触を試みている。そんな取材の過程で著者自身も織原から名誉棄損で訴えられ、著者自身が欧米とは異なる独特の裁判制度を体験することになった(結果は無罪)。そういったことすべてをひっくるめて、著者は「迷宮」あるいは「闇」(原題:People Who Eat Darkness)という言葉を選んだように思える。
世界中からさまざまな人種が集まる東京という大都会の夜の世界を描いて、第一級のノンフィクションであるのは間違いない。その本筋はひとまず措いて、僕がとりわけ面白かったのは、日本に20年暮らす著者のパリーにこの国がどんなふうに見えているかだった。滞在20年といえば、10代の日本人の若者よりこの国に長く住んでいることになる。だから日本のことはよく分かっている。でも慣れることはない。そんな視線が、いたるところに出てくる。
「この地を初めて訪れる外国人の多くは、それまで経験したことのない空気感に驚くという」とパリーは書いている。巨大都市であるにもかかわらず東京は清潔で、アジアの大都市の喧騒や薄汚さと無縁だ。「この街を包む無関心で静謐なフィルムの下には、機械のエネルギーと精密な効率性が隠されている」。そんな整然とした都市のなかで、初めて訪れた外国人は「謎だらけの可能性への曖昧模糊とした興奮」に捉われる。読むこともしゃべることもできない日本語。低いドアや天井、量の少ない料理に、「あたかも自分の体がひとまわり大きくなり」「肉体的に変身したかのような感覚」。
ルーシーが日本に到着して六本木に向かったのは春から夏へと移る季節だった。清潔な都市にも「夏が始まると、地中浅くに埋められた下水管から汚水のにおいがあたりに漂い出す。そんな予期せぬ第三世界の汚臭は、ピザや焼き鳥、魚、香水のにおいとまじり合っていく(不思議なことに、日本で人の汗のにおいを嗅ぐことはない)」。そして「外国人と遊びたい外国人」「外国人と遊びたい日本人」「日本人(女性)と遊びたい外国人(男性)」が集まる六本木は、「日本で唯一、ガイジンであることの疎外感──刺激的ではあるが、ときに残酷な感覚──が体と頭から離れる場所だった」。
ルーシーは日本に来て1週間もたたないうちに、六本木のナイトクラブでホステスとして働きはじめる。「ホステスの仕事とは具体的にどんなものか? 欧米人の耳には、その言葉は滑稽なほどいかがわしく、婉曲的だ」。行方不明のルーシーを探して来日した家族は、ホステスはコールガールとは違うことを、母国のジャーナリストに繰り返し説明しなければならなかった。確かにホステスはコールガールではない。でも著者は、「指名」や「ボトルキープ」や「同伴」といったボーナスとノルマを併せもった日本の水商売のシステムを明らかにしながら、「いったん水商売の世界に足を踏み入れると、女性は激しい誘惑とプレッシャーにさらされる」と書く。そんな「システム」の背後には、日本独特の性産業がある。
「世界のどこを探しても、これほどの豊かな想像力と創意工夫で性産業を発展させてきた国は、日本以外にないだろう。かれらが想像力を働かせる理由となったのが、中途半端で法的拘束力の弱い日本の売春防止法だ。日本の法律で唯一厳しく禁じられているのは、男女間の挿入、いわゆる“本番”のみである。フェラチオや自慰行為であれば、どんな形でも赦される。……核となる真実を覆い隠すため、性産業はありとあらゆる名前をつけてサービスを展開することになる」
パーリーの外国人としての目は、水商売ばかりでなく自身も被告となった裁判制度にも向けられている。著者が「厳格かつ滑稽で、気味悪くも退屈」と記す日本の裁判が欧米のそれといちばん異なるところは、例えばアメリカで約73%の“有罪率”が日本では99.85%に跳ね上がる、つまり「裁判になればほぼ有罪は確実」であることだ。そのことを前提に、著者は日本の裁判制度について書いたアメリカの社会学者の言葉を引いて、日本の裁判は喧嘩や戦いというより「儀式」であると書いている。
「日本の裁判所には、イギリスの法廷に見られるような芝居がかった崇高さは存在しなかった。…反対尋問はすべて型通りで、まさに拍子抜け。…雄弁な陳述も、パフォーマンスも、対立も、ドラマもない。たまに誰かが苛立つ程度で、それ以外は感情表現もほとんどゼロ。堂々たる法の審理というよりも、まるでどこかの学校の退屈な職員会議を見ているようだった」
さて本筋に戻ればパーリーは、織原が自分のマンションに誘い睡眠薬やクロロホルムで意識を失わせて多くの女性を犯し、時に死に至らしめた犯罪について、彼の生い立ちや外国人だった被害者の職業、あるいは社会のシステムといったことに因果関係を求めることも、批判することもしていない。
織原が大阪のパチンコ王である裕福な在日韓国人の家に生まれたこと。田園調布の家政婦つきの一軒家に独り暮らしながら慶應義塾附属高校に通っていたこと。この時期に日本国籍を取り四度目の改名(本名、本名の日本読み、日本の通名、国籍名)をしたこと。少年時代から友達と呼べる人間が一人もいなかったこと。それらを犯罪と関係する要因としてでなく、背景をなす事実として記している。
ルーシーがホステスという仕事を選んだことも、水商売のシステムが複雑なことも、それが犯罪被害者になることと直ちにつながったわけではない。ただ、ルーシーは織原の誘いに乗って海辺のマンションへ行ってしまった。多くの外国人にとって、そんな機会に遭遇すれば母国やほかの国でなら警戒心を働かせても、この国は安全な場所と感じられていた。
「似た状況に置かれれば、多くの若い女性が同じ行動を取っていたにちがいない。おそらく今後も、たくさんの女性が同じことを繰り返す。しかし、そのうち危害を受けるのはごくわずかにすぎない。これこそが、ルーシー・ブラックマンの死についての悲しくありふれた真実だった。私はそんなふうに考えるようになった。彼女は決して軽率でも愚かでもなかった。ルーシーは──安全ではあるが複雑なこの社会で──きわめて運が悪かったのだ」
映画やテレビドラマを見すぎの身には、なんだか物足りない、はぐらかされたような結論だけれど、そこに大人の国から来て年季の入った、そしてこの国をよく知ったジャーナリストの目を感じた。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





