騎士団長殺し【村上春樹】
騎士団長殺し
| 書籍名 | 騎士団長殺し |
|---|---|
| 著者名 | 村上春樹 |
| 出版社 | 新潮社(第1部512p、第2部544p) |
| 発刊日 | 2017.02.25 |
| 希望小売価格 | 各1,944円 |
| 書評日 | 2017.04.25 |
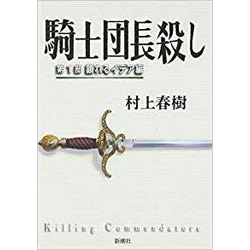
『風の歌を聴け』以来、村上春樹の長編はほとんど読んできた。群像新人賞を受けたこの小説が刊行されたのが1979年だから、ざっと40年になる。なんでこんなに長いあいだ飽きずに読んでこられたんだろうと考えると、同世代としての共感がいちばん大きかったように思う。小生は1947年生まれ、村上は49年、いわゆる団塊の世代に属する。それぞれの生きた道筋は違っても、いろんなことを同時代的に体験し同じ空気を呼吸してきた。そのことで、言葉以前に通ずるものがある、ような気がする。
村上春樹の初期の小説に流れていたのは喪失感と、にもかかわらず日々はつづく、という感覚だったと思う。『風の歌を聴け』は、東京の大学に在籍しているらしい「僕」が神戸に近い海沿いの町に里帰りして、なじみのバーで友人やガールフレンドととりとめない日々を過ごす小説だった。アメリカ西海岸ふうな舞台装置と、アメリカ小説から抜け出てきたような洒落た会話が新鮮だった。でも仲のよい友人と親しく会話をかわす「僕」の心の底に、どうしようもなく喪失感が流れているように感じられた。
それがなにに由来するかは小説では触れられないが、1970年前後に(たまたま同じ)大学にいた小生には、その心情はとてもよく理解できた。小生もまた同じような鬱屈を抱えていたからだと思う。そのような心を抱えているにもかかわらず人は生きていかねなばならず、朝は等しくやってくる。そんな穏やかな日、顔をなでる風と樹々の葉の匂いがたまらなく心地よい。そういう小説だった。
そんな喪失感は、その後の小説では友人の失踪やガールフレンドとの別れというかたちで造形される。例えば『羊をめぐる冒険』では、『風の歌を聴け』にも出てきたネズミと呼ばれる友人が失踪する。1970年前後に大学生だった者にとって、ある日、突然に誰かがいなくなるのは格別めずらしいことではなかった。新旧左翼のセクトの暴力的な衝突があり、そこから脱落していく者もいたし、地下組織に潜っていく者もいた。新興宗教のコミューンに参加していく者もいた。高度経済成長のさなか、なにをやっても食っていくことはできたから大学に見切りをつける者もいた。意識的にアメリカ西海岸ふうに仮構された小説世界でありながら、物語のなかで失踪したネズミの背後に、ある日キャンパスから姿を消したAやBといった知人の影を感じたものだった。そもそも『風の歌を聴け』の主人公「僕」にしてからが、大学から(一時にせよ)姿をくらましたのではなかったか。
『羊をめぐる冒険』には、羊の姿をした「羊男」が登場する。このあたりから村上春樹の小説は、現実とも非現実ともつかない寓話的な色彩をおびはじめた。二つのストーリーが同時進行したり、地上と地下・意識と無意識の世界を行き来したり、月がふたつある「1Q84」のようなもうひとつの現実が出現したり、物語世界が複雑になり重層化する。ささやかな日常世界と、ファンタジーあるいは3Dゲームのような寓話の世界と、哲学的な問答が共存して独特の世界をつくりあげていった。
この時期の村上春樹の像をイメージすると、いま立っている地球上の一点から、地上世界には目もくれず地下をドリルでどんどん掘り下げている、といった印象になる。現実世界を意識的に避ける姿勢は明らかだった。それが変わったのは、村上自身が「コミットメントを考えるようになった」と語っているように、彼の故郷を襲った阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件に遭遇してからだろう。サリン事件の被害者に話を聞いたノンフィクション『アンダーグラウンド』(未読)を経て、やがて小説世界にも歴史的な出来事や事件が顔を出すようになった。『ねじまき鳥クロニクル』ではノモンハン事件が物語に組みこまれ、『1Q84』ではオウム真理教に似た新興宗教の教祖が登場した。
もっとも小説世界に現実の出来事をもちこみ、それをフィクションとして成功させるのは極めてむずかしい。歴史的事件や現実の重みに対抗するのは至難の業だからだ。村上春樹の場合、現実世界の出来事を正面きって取り込むのでなく、いくつかの媒介や抽象化をほどこして、いわば寓意として小説世界に組み入れる戦略を取った。そしてそれは、これまでのところうまくいっていると思う。
『騎士団長殺し』で触れられているのは、ナチスによるオーストリア併合と南京大虐殺である。それが「邪悪なる父」と「殺し」という抽象化をへて登場人物の画家と彼の絵画の謎に結びつく。
主人公の「私」は、企業の社長室に掛けられるような肖像画を生業とする画家。妻の「ユズ」から離婚を告げられ、友人の父で高名な日本画家・雨田具彦(ともひこ)が住んだ小田原の山荘に仮住まいすることになる。ある日、「私」は天井裏に隠された雨田の奇妙な絵画を見つける。モーツァルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」の「騎士団長殺し」の場面を飛鳥時代に翻案した「暴力的な」日本画だった。
同じころ「私」は谷向かいの邸宅に住む免色(めんしき)なる人物から肖像画を描いてほしいと頼まれる。免色は、やはり谷向かいに住む少女まりえの家を夜ごと双眼鏡で観察している。まりえは自分の娘かもしれない、と免色は「私」に告げる。ある晩、どこからか鈴の音が聞こえてくる。免色と「私」が音の出どころである古井戸を暴いたことから、絵画のなかの騎士団長が「私」のアトリエに出現する……。
これまでの村上春樹の小説に現われたあらゆる要素が取り込まれている。次から次に謎が提示され物語を駆動するミステリー的要素。「私」と「ユズ」の、離れ離れになった男と女のラブ・ストーリー。魅力的な美少女の存在。音楽(クラシック、とりわけオペラ)や映画への愛。昔の洒落た会話とはひと味違うユーモア。エロスをまったく感じさせないセックス描写。絵画から抜け出た「騎士団長」の活躍と、「イデア」や「メタファー」をめぐる哲学問答。現実と非現実の二重構造。地下(集合的無意識)世界の迷宮巡りと生還。そうした諸々の要素が巧みなストーリー・テリングによって組みたてられ、村上春樹の暗黒ファンタジーとでも呼べそうな世界を堪能することができる。
物語を通底するキーワードは、タイトルにも採られた「殺し」。雨田の絵画「騎士団長殺し」は、ドン・ジョバンニが騎士団長を剣で刺殺する殺人の場面。その絵画から抜け出た騎士団長を、「私」はもう一度殺すことによって地下世界への鍵を手に入れ、失踪した(ここでも!)まりえを救出する。家を出た「私」は車での旅の途中、一夜を共にした女に「首を絞めて」と頼まれ本当に女を殺しそうになる。「私」のなかにもある暴力への衝動、「毛深い獣の体臭」を伴った激しい怒りを「私」は無自覚なまま他人の肖像画に描きこんでいた。
ところで「騎士団長殺し」を描いた雨田は、彼が若き洋画家としてウィーンに滞在していたとき、恋人が反ナチの地下抵抗組織に属していたことから逮捕され、彼自身も国外に追放されていた。また雨田の弟は一兵士として南京攻略戦に従軍し、上官に命じられて中国人の首を斬ったことを苦に自殺していた。「騎士団長殺し」は、雨田がそうした体験への怒りと恐怖と絶望から描いた鎮魂画で、誰にも見せることなく屋根裏に秘匿していたのだった。
ここ何作かの村上の小説には、それまでほとんど感じられなかった父、あるいは父性への関心が登場する。登場人物の父親であったり、もっと集合的な(南京虐殺を引き起こした)父親世代であったり、さらに抽象化されて父性という観念であったりする。そして村上の場合、父あるいは父性は人間のもつ根源的な暴力への衝動と分かちがたく結びついているように見える。小説のなかで記される「邪悪なる父」という言葉がそれを象徴しているだろう。
もうひとつ、これは小生の思い込みかもしれないが、雨田具彦という洋画から日本画に転向した大家の背後に、藤田嗣治と横山大観という二人の巨匠の影を感じたことを記しておこう。藤田と横山は、太平洋戦争時に積極的に軍部に協力したことで知られる。藤田は何枚もの戦争画を描き、横山は大日本帝国の象徴としての富士山を描いた。戦後、藤田は絵画界の戦争責任を一身に背負わされて祖国を捨て、横山は富士山を帝国の象徴から平和の象徴へと読みかえて大家としての生をまっとうした。
藤田にはノモンハン事件を描いた「哈爾哈(ハルハ)河畔之戦闘」という戦争画がある。藤田がこの絵を描いた時代には、日本軍が惨敗したノモンハン事件の実相は国民に知らされていなかった。藤田の絵は、銃剣を手にした草原の日本兵がソ連軍戦車によじのぼっている、日本軍の勝利を伝えて奇妙に明るい作品になっている。ところが近藤史人『藤田嗣治 「異邦人」の生涯』によると、藤田にはもう一枚の「哈爾哈河畔之戦闘」があり、彼のアトリエでそれを見たという証言がある。証言によると、もう一枚の「哈爾哈河畔之戦闘」は、ソ連軍の戦車に踏みつぶされた日本兵の死体が累々と重なる凄惨な絵だったという。それがどんなものだったかは、同じように死者が折り重なる「アッツ島玉砕」から想像できよう。
藤田のもう一枚の「哈爾哈河畔之戦闘」は本当に存在したのか。存在したとしたら、藤田はそれを処分してしまったのか。謎のままだ。でも村上春樹が描写する「騎士団長殺し」は、そんな秘められた絵画の歴史を踏まえているようにも感ずる。とすれば村上春樹は、ここでもまた幾重もの媒介を通して歴史と相渉っていることになる。もっとも、『ねじまき鳥クロニクル』で描写された兵士が人間の皮膚を剥ぐひりひりした感覚や『1Q84』の殺人を巡る問答が、読み手の現在につながっていると感じられるのに比べると全体としてファンタジーの色合いが濃い。
地下世界から生還した「私」は、再び日常の世界に戻ってゆく。地下世界の「邪悪な力」に触れ、しかしその誘惑に負けず逆に「生きるための熱源」を受け取った「私」は、子供を産んだ「ユズ」と再び一緒に暮らすことを選ぶ。『1Q84』がそうだったように、希望を感じさせるエンディング。そういえば、かつて村上春樹の小説の主人公は共通して「やれやれ」が口癖だったけれど、この小説の「私」は「やれやれ」とは一度も口にしないのだった。(山崎幸雄)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





