科学哲学【サミール・オカーシャ】
科学哲学
| 書籍名 | 科学哲学 |
|---|---|
| 著者名 | サミール・オカーシャ |
| 出版社 | 岩波書店(199p) |
| 発刊日 | 2008.3 |
| 希望小売価格 | 1575円(税込み) |
| 書評日等 | 廣瀬覚訳 |
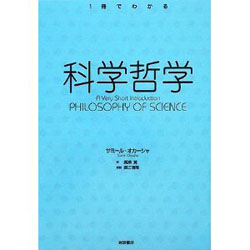
「岩波の「一冊でわかる」シリーズの最新刊。40年ほど前に大学のゼミでカール・ポパーの「歴史主義の貧困」を読み、社会科学方法論だ、記号論理学だ、確率論だと語り合っていた時代を過ごしているので、今の「科学哲学」という学問の状況は、何が変わり、進化したのかをおさらいしてみたいとのノスタルジーもあって読んでみた。
本書はまず、科学とは何かという問いかけから始まり、科学的推論、科学における証明、科学の変化と科学革命、物理学・生物学・心理学における哲学的問題、といった問題を取り上げていて、極めてスタンダードな構成といえる。
特に、最初の「科学とは何か」という導入は、大学の新入生の教養として科学哲学を学ぼうとするには既存の知識の再構築という観点からも有意義だ。科学史の知識はどうしても断片的となってしまいがちであるが、まず大括りの理解をすることが出来る。
通読した感想としては、以前(40年前)に比較すると、「科学哲学」の世界は方法論や考え方といった領域のウエイトが相対的に軽くなり、科学史やパラダイム・シフトの構造といった論点にウエイトが移ってきたという実感が強い。本書の楽しみ方は、科学史や方法論の基礎のおさらい、科学におけるパラダイム・シフトの構造や最新の科学領域(認知科学・生物学)での論点理解といったところだろう。
本書記載の科学史をおおまかに概括してみると、まずお約束のコペルニクスがまず登場。
プトレマイオス天文学(地球中心宇宙モデル)を攻撃した一冊の本がでたのが1543年。言わずと知れた、ポーランドの天文学者コペルニクスによる太陽中心宇宙モデルの提案である。この革新的提案は以降ケプラーやガリレオによって近代物理学の発展につながっていくのだが、ガリレオは数多くの天文学的発見を重ねて、真の意味での「最初の近代的な物理学者」といわれるにいたる。
その理由は、「・・・彼は、物質世界に存在する現実の物体----落体や投射体など----の振舞いを記述するのに数学の言語が使えることを始めて示した。・・・ガレリオの当時、これはけして自明のことではなかった。数学は純粋に抽象的な対象についての学であり、現実の物理的対象に当てはめることはできないと一般には考えられていた。・・・もうひとつの革新的なことをあげると、実験によって仮説をテストすることの意義を強調したことだろう・・・」
そして、1687年にニュートンはデカルトの「機械論の哲学」を進化させて「自然科学の数学的原理」を発表し、万有引力と運動法則の力学理論を確立した。「・・・ケプラーの惑星運動の法則とガリレオの自由落下の法則が彼の運動と引力の法則から論理的に帰結することを示した点である。・・地上と天上の物体の運動は同じ法則によって説明されるということだが、その法則をニュートンは厳密に定量的に定式化してみせたのだ。」このニュートン物理学は後、約200年間の科学の枠組みとなる。
このパラダイムを変えたのが、20世紀初頭にアインシュタインの「相対性理論」と「量子力学」という二つの革命である。相対性理論は、きわめて質量の大きな物体やきわめて高速で運動する物体にニュートン力学を適用しても正しい結果が得られないことを示したし、量子力学は、素粒子のようなごく小さなスケールの世界でニュートン力学が成り立たないことを示した。
こうした、物理学での革命的出来事以外の領域での変革は、生物学でいえば1859年のダーウィンの「種の起源」。そして、1953年ワトソンとクリックがDNAの構造を突き止めたことだといえる。その後の科学分野(この30年間ぐらい)で変革領域は、コンピータ・サイエンス、人口知能研究、言語学、神経科学などが挙げられるが、その中でも重要な領域は「認知科学」の進歩といわれている。それは人間の知覚・記憶・学習・推論といった活動を研究対象としているのだが、「人間の心がある点でコンピュータに似ており、人間の心的過程はコンピュータの実行する演算になぞらえて理解できる」というアイデアである。
この分野の発展によって、伝統的な心理学はすっかり様変わりしてしまった。認知科学はいまだに揺籃期とはいえ、心の動きの多くがこの学問によって解明できると大いに期待されている。
こうして概観しただけでもこの500年間の科学における革新( パラダイム・シフト)はドラマのようであり、人類の知的好奇心の壮大さがわかるだけに、そうした転換点における知的リーダーたちの「発見の文脈」に着目したトマス・クーンの「科学革命の構造」が注目されてきたという訳だ。
科学哲学の方法論の分野を俯瞰すると、「反証可能こそ科学理論の根本特徴」とする考え方や、「推論」「説明」「IBE( Inference of the best explanation)」「確率」といった手法や基本的な考え方が論理実証主義の観点で構築されてきた。しかし、1962年にトマス・クーンが発表した「科学革命の構造」によって大きな議論が巻き起こった。論理実証主義者は、「発見の文脈」と「正当化(証明)の文脈」を分離すべきものととらえ、「発見の文脈」は主観的・心理的プロセスであり、厳密なルールに支配されていない、一方「正当化の文脈」は客観的・論理的プロセスである、と考えた。その結果、論理実証主義においては「発見の文脈」としての科学史にそう重きを置かなかったという実態があった。
一方、クーンの言わんとしたところは、革命的なパラダイム・シフトが起こっている時期と通常の時期における科学的発想の差があることを指摘し、「発見の文脈」での科学者の意識や社会を含めた学者集団のパラダイムまでその論点を広げたことだった。もうひとつ、クーンの主張の主要な点は「科学の理論選択にアルゴリズムはない」とするものである。論理実証主義の科学哲学では「競合するふたつの理論とデータ集合が与えられると科学的方法の原理を用いてどちらが優れているかを決定できる」との意見が主要であった。
現在は「科学の理論選択にアルゴリズムはない」とする考えに賛成する学者も多くなっ物学や認知科学や環ているものの、当時、このようなクーンの主張は過去の古典的科学理解で自明視されていた科学の合理性や客観性などの見直しをも含意していたため、科学者達からは「科学の価値を貶めかねない、非合理的で反科学的な雰囲気」をもっていると批判された。こうして科学者と科学哲学者との間での相克も起こった。
しかし、分子生物学や環境科学、認識科学といった現代科学領域では世界観・パラダイム・文明といった社会との連携が必須であり、ますます科学哲学者と科学者のコラボレーションの重要性が増しているのは紛れもない事実となっている。
まだまだこうした議論は深化していくのであろうが、「科学の進化は人類の役に立つ」という原点に立つのであれば、「なぜ」という問い掛けに対して常に回答していくという責任が科学者と科学哲学者の双方に重く圧し掛かってきているのが現代であるということだろう。
なかなか面白く読んだが、「巾広い読者が予備知識なしに読める一冊」といううたい文句は少し無理がありそうに思えるが、どうか。(正)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





