境界の発見【齋藤正憲】
境界の発見
| 書籍名 | 境界の発見 |
|---|---|
| 著者名 | 齋藤正憲 |
| 出版社 | 近代文藝社(190p) |
| 発刊日 | 2015.12.15 |
| 希望小売価格 | 1,620円 |
| 書評日 | 2016.05.17 |
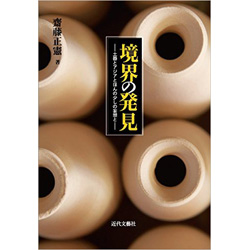
本書のサブタイトル「土器とアジアとほんの少しの妄想と」とあるように、広域アジア(最西端のエジプトから最東端の日本・インドネシアまで)における土器の製造技術を地域ごとに比較・検証するという、土器・陶器好きにとってはなかなか興味深い一冊である。ただ、土器といっても考古学的な研究成果を描いているのではなく、現在、アジア各地域の人々が製造・作成する日常品としての土器が対象である。フィールドワークを通して現地での調査を行っており、必然的にその地での生活に接していくことから、結果として、比較対象は土器を超えて文化や食にまで広がっていき、そこから紡ぎだされてくる広域のアジア観を「境界」と「辺境」という概念を導入して構成しようとするものだ。
今まで多くの学者・知識人たちが提示してきたアジア観も紹介しつつ、自説、著者の言い方を借りると「妄想」、を提示している。土器を探し求めて歩き回る中で著者は自身のアジア観が常に修正を求められてきたと書かれているのが印象深く、体験や実感によって理論を随時見直していくというフィールドワークの価値がそこに示されていると言える。
こうした、文明論を語るとき立ち返る原点として、和辻哲郎、丸山真男、梅棹忠夫といった先人達の成果が本書でも多く引用されていて、団塊の世代たる評者としても思い起こされる懐かしい名前が並ぶ。特に梅棹の「文明の生態史観」に刺激を受けた学生の頃を思い出しつつ本書を読み進んだ。著者の齋藤は今日のような、世界の各地で国家間・民族間・宗教間の衝突や混乱が起こっている時こそ、一人ひとりがアジア観や世界観を持つ必要性を次のように表現している。
「アラブの春、イスラミックステート(IS国)との戦い、など普通の日本人の常識を超えてしまっている。しかし、ここから逃げるのではなく、翻弄されるだけでない自らの拠って立つところを見失うことなく事態を見定める余裕が欲しい。……日本人である私たちはアジアの一員である。だからアジア観を涵養することが大切だ」
本論の土器について話を戻すと、土器の製作は古くから確立した技術があったのだが、中国で発明された陶磁器の技術によって、日本をはじめ、またたく間に世界の土器文化は浸食されていった。それでも世界に目を向ければ細々ながら土器が生活の中で生きている地域は存在し、そうした地域、エジプト、バングラディシュ、インドネシア、台湾、を訪ねて現代に残された伝統的な土器製作技術や暮らしを調査した記録である。
エジプトでは乾燥地帯だけに気化熱で水を冷却させるための素焼きの水瓶が必要であること、インドでは浄・不浄の観念が根強く、他人の使用した食器を使うのを忌避するので使い捨て出来る土器食器が使われているといったように、地域毎に土器の文化が残って来た理由も様々であるが、底流の文化や気候的条件を理解することで得られる納得感は理屈で説得されるのとは違った楽しさが感じられる読書の大きな要素だ。
各地域の土器作成の技術を比較するポイントは、まず焼成技術としての窯の構造であり、燃焼室の有無、焼成室の構造(閉空間か開空間になっているか)といった構造比較である。次に、土器を粘土から成形する技法であるが、ロクロ成形か叩き成形か、ロクロ成形としてもロクロ自体の形状や機能の相違が検証対象となる。
西アジア(乾燥)の代表格のエジプトでは、ナイル川下流デルタ地帯とナイル川上流地域で土器製造が盛んだが、ロクロ成形や燃焼室と焼成室の機能を確立させた窯による伝統的土器作りが見られる。そして、東アジア(湿潤)の代表格の台湾に目を向けている。台湾は典型的な米食文化。また、土器の作成技術として台湾では叩き成形である。この土器作り方法の違いは、ロクロ成形が回転力を使った均整の取れたフォルムをとるのに優れた技術である一方、叩き成形の特徴を、丁寧にたたき続けることで達成できる均一な器厚であり、それは調理、さらに踏み込めば炊飯に関して厚さが一定である方が器は割れ難いとしている。これは米食文化の器として必要な特性である。また、焼成方法は野焼きに近く、土器を燃料で蔽って焼くという、窯を作らない手法が取られている。
こうした、まったく異なる特性を持った西アジアと東アジアの土器製作も地理的中間地帯では複雑な様相を呈すことになる。例えば、バングラディシュの土器作りでは本体成形にロクロを使い、壷の口縁部分は叩き成形で作って、合体させるという技術の折衷が見られる。焼成窯の構造でも燃焼室を持ちつつ、焼成室は無く、土器を藁で蔽った上で全体を泥でコーティングして焼成するという構造など西(乾燥)と東(湿潤)の技術を「土器作成のプロセス全体にみられる融合と折衷」を見出すことが出来る。
この地域は湿潤アジアの縁辺にあって、乾燥アジアに対する前線を占めている。こうした地域を、単に土器作成技術という側面だけでなく、地理的・環境的にも「境界」と名付けているのだが、それは方向性や優劣を喚起しないために敢えて「境界」という言葉にこだわっている。また、対比的にインドネシアの土器作りを検証しているのだが、そこではロクロ成形も叩き成形も行われていて、一つの窯場や村の単位では単一の技術が使われているという。ある窯は叩き成形、ある窯ではロクロ成形といった具合の技術混合である。この地域の技術混合を著者はこう解釈している。
「インドネシアの陶工は新しい技術を積極的に導入し、改良を加えながら古い技術も温存している……この辺境アジアでは技術は折衷せず、共存した。これが『境界』と『辺境』の違いとなっている」
文化的にみるとバングラディシュもインドネシアもともにヒンドゥーが伝統文化であったところにイスラム文化がやって来たという図式は同じである。この二つの地域(「境界」と「辺境」)の違いはなにかを著者は新しい文化の流入スピードの差であり、そこから生まれる受容プロセスの差としているのが面白いところだ。
「前線に近く、影響を受けるスピードが速ければ、ぶつかり合う二つの文化の争いになるが、どちらかがゼロになることはなく、結果として折衷が生まれる。一方、ゆるやかな変化とは戦いではなく共存となり、そして乗り換えることに値する技術が開発されると、新しい技術を受け入れる。柔軟性があるだけに優れたもの、効率的なものに置き換えられていく。……この二つの技術受容のプロセスの違いこそが『境界』と『辺境』の違いである」
前線と後方の違いに注目するとともに、乾燥と湿潤の二元的な考え方について、著者はこうしたまとめ方をしている。
「小異に目をつむり、大同を見定めようとすれば……攻撃性、積極性、展開力、発信力に勝る乾燥アジアに対して、湿潤アジアは受動的、忍従的だが感受性、応用力に優れている。これは拡大することで歴史を動かしてきた乾燥アジアと、嵐のようなその影響に晒されつつも冷静な判断力を以って、懸命に切り抜け、活路を見出してきた湿潤アジア」
そして日本はどうなのかというと、著者の考えは、日本は「境界」ではなく「辺境」という説に立っている。土器からの検証ではないものの、技術受容のブロセスや応用力などは、明治以降の日本における製造技術の吸収と発展の歴史であり、「辺境」特性そのものとも言える。
沢山のヒントが提示されている本書は、自分なりの考えや答えを出したくなる一冊といえる。読み終えて著者の紹介に目を通したところ、1971年生まれとある。和辻や梅棹といった学説に対する懐かしさからか著者は私と同年代の団塊の世代かと想像して読んでいたのだが、ずっと若い人であったことに驚いた次第。(内池正名)
| 書評者プロフィル | 編集長なんちゃってプロフィル | 免責事項 |
Copyright(c)2002-2010 Kenji Noguchi. All Rights Reserved.





